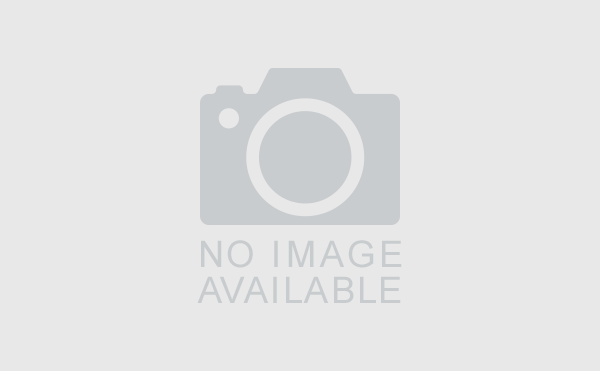梅干しについて その1
今年の冬はあまり雪が降らず、乾燥している日が多いですね^^;
ウイルスちゃんは乾燥が得意で私達人間の粘膜も乾燥してしまうと防御機能が下がってしまい、
ウイルスが簡単に身体に侵入してしまいます。
マスクやうがい、手洗いを徹底して体調を崩さないようにしたいですね。
さて、今回は、梅干について2回に分けてお伝えいたします。
皆さんは梅干しを想像しただけで唾液が出て来ることはありませんか?
梅の起源はいつなのか、何故身体にいいのか調べてきましたので、御覧くださいね(^o^)
日本の梅は中国からの移植説と日本古来の原産地説とがあり、
定かではありませんが文献・学者の多くは中国原産地説をとっています。
日本では、花がまず人々の関心をひき果実の利用はその後になったのに対し、中国では果実の利用が先であったようです。
梅干しが食卓に上がるようになったのは、江戸時代からでそれ以前は「縁起物」や「薬」などとして珍重されていました。

古くから梅干しは「三毒を絶つ」と言われ、強い殺菌作用が食中毒や感染症に有効だとされています。
ちなみに三毒とは食べ物・水・血液に含まれる毒のことです。
昔の旅人は必ず梅干しを持ち歩いたそうです。
旅先での食あたりや水あたり、風土病などに効果を発揮していました。
旅のお守りと言えばまずは梅干しだったようです。
梅干しの効能と言えばまず思い浮かぶのがあのすっぱさの元であるクエン酸です。
クエン酸は唾液の分泌を促し、疲労回復や解熱、便秘解消などに効果があります。
クエン酸の他には「リグナン類」と呼ばれる成分が多種含まれています。
リグナン類は抗腫瘍活性、抗酸化活性、抗肥満活性の性質を持ちます。
梅が持つリグナンは食中毒予防、インフルエンザ予防、糖尿病予防、血液浄化作用などに代表される多くの効能や健康効果があることが実証されています
今回はここまでとさせていただきます。次回の梅特集もお楽しみに!