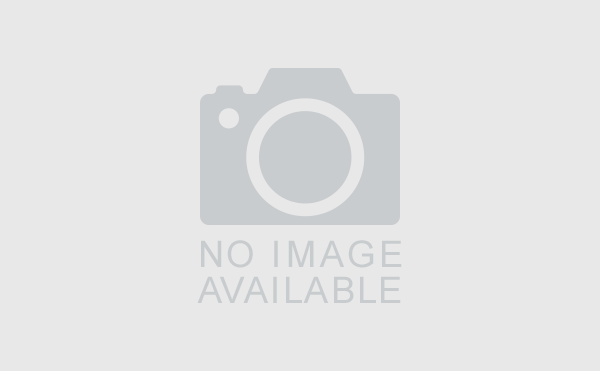全日本鍼灸学会報告③「気象関連痛(天気痛)のメカニズムと対策」
「気象関連痛(天気痛)のメカニズムと対策」というテーマで中部大学の佐藤純先生のご講演。
「天気を病む」なんて言う方も多いのではないでしょうか。
東洋医学ではもともと人は天気に影響を受けていると考えられていましたが、西洋医学では5,6年前まで「天気痛」なんてないという方が多かったようです。
ところが研究が進み明らかに気象により身体は影響を受けている事がはっきりしてきました。
実際に天気により体調の変化を感じるという人は女性の50%、男性の23%いるようです。
症状としては頭痛、肩こり、倦怠感、めまい、関節痛などで1番多いのは頭痛で68%を占めるようです。
天気痛は何に影響を受けており、どのタイミングに発症するのかというと、気圧に影響を受けており、気圧が急に下がった時や急に上がった時に症状が出やすいようです。
気圧の変化により体で何が起きているかというと交感神経緊張、血圧上昇、心拍の上昇などが起きているようです。
気圧の変化をどこが感じているかというと実は耳の中のようです。
内耳に気圧センサーがあり過敏な人は影響を受けてしまうようです。
また佐藤先生からの話ではないですが、気圧の低い環境では人間の体は膨張し、内圧が高まっているようです。
気圧の低い山の上ではポテトチップスがパンパンに膨らんでしまうように。
重力と気圧は地球が出来てからずっと変わらない外的な要因のようです。
どんなものも膨張すると温度が下がり、水分をため込みやすくなり、流れが悪くなるようです。
そんな気圧の影響を軽減するためにどうしたらいいのか…?
まずは日ごろの自律神経の状態を安定させることや予め気圧が変動するタイミングを知り対処するようにする。
あとはストレスを貯めないとか軽い運動をするとかその季節にあった養生がとても大事になってくるようです。
また佐藤先生おすすめの耳体操も予防効果があるようです。
もちろん鍼灸治療も効果的です!
東洋医学的な視点から水分の代謝を改善させたり、内示、前庭覚の機能を改善させることで対応してきます。
地球上で生活する以上、気象の変化にどう適応させていくかは大きな課題であり、避けて通れない影響だと思います。

佐藤先生の書籍も大好評!