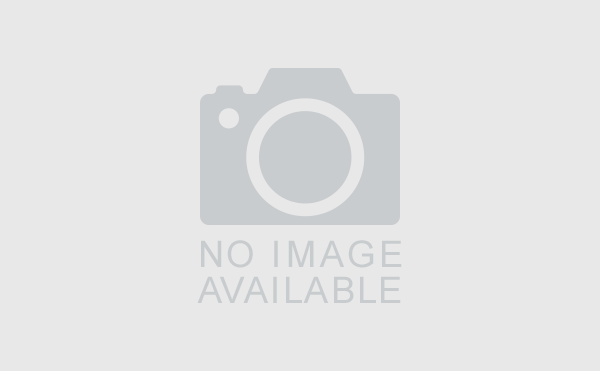冷たいものの取り過ぎと胃腸のお話

皆さんこんにちは!くま鍼灸院スタッフの飯塚です(*^^*)
さて、今回のブログのテーマはちょっと季節外れですが、冷たいものとりすぎと胃腸についてです。
冷たい食べ物、飲み物は美味しく感じて過剰に摂取したくなりますね^^;
しかし、何に対しても過剰は良くないことです。
特に冷たいものや冷たい飲み物は内蔵を冷やしすぎて、血行障害を起こします。
口腔内や咽頭は冷たいものは通りすぎるだけですのでそこまで影響はないのですが、胃に関しては飲食物が一時停滞するために胃壁を冷やしてしまいます。
胃壁の血流が悪くなることにより消化がうまくいかなくなり、小腸・大腸にも悪い影響が出てきます。
夏の身体は、冷房の影響などで身体の外側からと、冷たいものの飲食で身体の内側から冷えがちです。
秋の身体がまだ夏モードで冷やす方向に働いているので、寒くなり始めは要注意です。
特に10/20~11/6の秋の土用の時期は体調を崩しやすいので気を付けましょう!
身体が冷えると、血のめぐりが悪くなり、胃の働きも弱くなってしまいます。
そもそも、胃に食べ物が入ってくると、それを消化するために、まず胃酸が分泌されます。
胃酸は胃壁(いへき)も溶かしてしまうほど非常に高い酸性度です。
胃酸から胃壁を守ってくれているのは胃の粘膜ですが、冷房により身体が冷えたり、冷たい飲食物が胃に入ってきたりすると、胃粘膜の血行が悪くなります。
すると、胃壁を守る粘液が充分に分泌されなくなり、胃酸が胃壁を傷つけ、胃痛につながるようです。
また、夏冷えで胃が弱っている状態にストレスが加わると、交感神経が過度に優位になり、胃の働きを強めようとして、胃酸が多く分泌され、胃痛の悪化を招きます。
(https://www.well-lab.jp/ ウェルラボより引用)
冷たいもののとりすぎによって腸で起こる変化は一番に免疫機能の低下が挙げられます。
腸壁が36℃以下になると免疫細胞や腸内細菌叢(腸内フローラ)の働きが悪くなり雑菌やウイルスなどに太刀打ちできなくなってしまい免疫機能が低下します。
また、日本人は食生活の欧米化に伴って腸内環境が変化してきています。
最近では、自己免疫疾患やアレルギー疾患は、ある腸内細菌の減少が制御性T細胞という過剰に働く免疫にブレーキをかける役目を持つ細胞の減少を引き起こしているのではないかと言われています。
その辺の話はまた次回お伝えしますね!